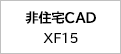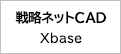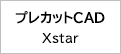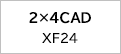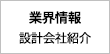NSC-Xstar
�yNSC-�����d�v�Z�z
+�@�S�ēW�J�@�b�@-�@�S�Đ܂肽����
���o���̎�ʂ͎����Ŕ��f�ł���ꍇ������܂����A�����Ŕ��f�ł��Ȃ��ꍇ������܂��B�����Ŕ��f���ł��Ă��Ȃ��ꍇ�́A�������̌v�Z���ʉ�ʂŎ��o���̐ݒ��ύX���āA���Ή������肢�v���܂��B
�ύX���@�̏ڍׂɂ��܂��Ă͎������Q�Ƃ��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�ύX���@�̏ڍׂɂ��܂��Ă͎������Q�Ƃ��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
NSC-Xstar����������Ă��Ȃ�CAD�Ŕz�u�������́A���^�C�v�̑����������Ă��܂���̂ŏ����ƂȂ�܂��B
���̏ꍇ�A�u�\���v�Z�^���^�C�v�ꊇ�ύX�v�����s���Ă��������B�ꊇ�Łu�������v�ɕύX����܂��B
��NSC-Xstar����������Ă���CAD�ŁA�����̊O�i�ꕔ�ł������ɂ������Ă���ꍇ�͏����j�ɔz�u�������͎����ŗ��^�C�v���u�������v�ƂȂ�܂��B���������[���̕����ɂ������Ă���ꍇ�́u�����v�ɂȂ�܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
���̏ꍇ�A�u�\���v�Z�^���^�C�v�ꊇ�ύX�v�����s���Ă��������B�ꊇ�Łu�������v�ɕύX����܂��B
��NSC-Xstar����������Ă���CAD�ŁA�����̊O�i�ꕔ�ł������ɂ������Ă���ꍇ�͏����j�ɔz�u�������͎����ŗ��^�C�v���u�������v�ƂȂ�܂��B���������[���̕����ɂ������Ă���ꍇ�́u�����v�ɂȂ�܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�؍ފ���x�v�Ɓu�Œ�d�v�̂݁ASTRUCTURE�̕W���}�X�^�[�́u�\���v�Z�W���ݒ�c�[���F���x�p�����[�^�^�u�v�u�d�}�X�^�[�ҏW�F���ljd�A�O�ljd�A���d�A�����d�v����NSC�̃}�X�^�[�֕ϊ����\�ł��B
���}�X�^�[�p�X�ؑւō쐬�����}�X�^�[�̕ϊ��ɂ͑Ή����Ă���܂���B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
���}�X�^�[�p�X�ؑւō쐬�����}�X�^�[�̕ϊ��ɂ͑Ή����Ă���܂���B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)�L���f�ʐ� Ae �� Ao �~�i���f/���j
�@Ao�F����|�������Ȃǂ̒f�ʐρimm2�j
�@���f�F�d���镔���̐��i�����j
�@���F�����imm�j
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�����H�@�̏ꍇ�͗L���f�ʐς͍l�����Ȃ����߁u�[�v�ƕ\������܂��B
�����H�@�̏ꍇ�̌v�Z���@�́A�u���ˍޒ[���ڍ����̐v�v�͗L���f�ʐς��l�������A�����}�X�^�[�̋��e����f�ϗ͂Ō�����s���܂��B
�u���̂߂荞�݂̌����v�̂ق��ʐς��v�Z����ۂɁA�����̃p�[�X�p�̉��H�a��莩���I�Ɍv�Z����Ă��܂��B
�ʐς̐��l�̓v���O�����Œ�ŕύX�͂ł��܂���B
�������v�Z���ꂽ�ʐς���ύX�������ꍇ�́A���̑�������蓮�ŕύX���Ē����܂��悤���肢�v���܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�����H�@�̏ꍇ�̌v�Z���@�́A�u���ˍޒ[���ڍ����̐v�v�͗L���f�ʐς��l�������A�����}�X�^�[�̋��e����f�ϗ͂Ō�����s���܂��B
�u���̂߂荞�݂̌����v�̂ق��ʐς��v�Z����ۂɁA�����̃p�[�X�p�̉��H�a��莩���I�Ɍv�Z����Ă��܂��B
�ʐς̐��l�̓v���O�����Œ�ŕύX�͂ł��܂���B
�������v�Z���ꂽ�ʐς���ύX�������ꍇ�́A���̑�������蓮�ŕύX���Ē����܂��悤���肢�v���܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u���ʗ̈�v�̓��͖����ł������d�v�Z���s�����Ƃ��\�ł��B
���ʗ̈斳���Ōv�Z����ꍇ�A�����ݒ�^�\���v�Z�ݒ�^�v�Z�����^�u�́u���̈敪�����@�v�ŁA�u���������v�܂��́u�T�b�����v��I�����Ă��������B�u�����\�ʂ��Q�Ɓv��I�������ꍇ�́u���ʗ̈�v�̓��͂��K�v�ł��B
�܂��A�u�n����v�̈ʒu�ɂ���ĉ����d�ŏE���̂�����d�ŏE���̂��ʂ��܂��̂ŁA�u�����i�����j�ʗ̈�v�̓��͂��Ȃ��Ă������\�ł��B
�������A�����`��ɂ���Ă͐���ɔ���ł��Ȃ����Ƃ�����܂��̂ŁA���̏ꍇ�́u�����i�����j�ʗ̈�v�̓��͂��K�v�ƂȂ�܂��B
���ʗ̈斳���Ōv�Z����ꍇ�A�����ݒ�^�\���v�Z�ݒ�^�v�Z�����^�u�́u���̈敪�����@�v�ŁA�u���������v�܂��́u�T�b�����v��I�����Ă��������B�u�����\�ʂ��Q�Ɓv��I�������ꍇ�́u���ʗ̈�v�̓��͂��K�v�ł��B
�܂��A�u�n����v�̈ʒu�ɂ���ĉ����d�ŏE���̂�����d�ŏE���̂��ʂ��܂��̂ŁA�u�����i�����j�ʗ̈�v�̓��͂��Ȃ��Ă������\�ł��B
�������A�����`��ɂ���Ă͐���ɔ���ł��Ȃ����Ƃ�����܂��̂ŁA���̏ꍇ�́u�����i�����j�ʗ̈�v�̓��͂��K�v�ƂȂ�܂��B
�u�\���v�Z�^�댯���F�����\���v���j���[�ŁA�\����ON�^OFF��ݒ肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
�܂��A�u�⏕�^���ݒ�^�E�N���b�N���j���[�ݒ�v�œo�^���邱�ƂŁA�R���e�L�X�g���j���[�ł̐ؑւ��\�ł��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�܂��A�u�⏕�^���ݒ�^�E�N���b�N���j���[�ݒ�v�œo�^���邱�ƂŁA�R���e�L�X�g���j���[�ł̐ؑւ��\�ł��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
����A�w1�́u�����v�ɑ��āA�����́u�����i�����j�ʗ̈�v���܂܂��v�Z���ł��Ȃ��x�Ƃ����d�l�ł��B���̂��߁A��{�I�ɂ͉��L�̂Q�̕��@�̂����ꂩ�œ��͂��Ē����悤���肢�v���܂��B
�@�u�����v���P�ɓ������ē��͂�����ԂŁA�u�����i�����j�ʗ̈�v���P�̎d�l�ɓ������ē��͂���B
�A�u�����v���u���������\�ʁv�̗̈悲�Ƃɕ������ē��͂���B
���w1�́u�����i�����j�ʗ̈�v�ɑ��āA�����́u�����v���܂܂��v�Z�x�ɂ͑Ή����Ă��܂����A���Ⴂ�̉����̂悤�Ɂu�����v�̓��͔͈͂��d�Ȃ�ꍇ�́A�����ʂ��Ƃɉ����ʗ̈�����ē��͂��Ă��������B
�@�u�����v���P�ɓ������ē��͂�����ԂŁA�u�����i�����j�ʗ̈�v���P�̎d�l�ɓ������ē��͂���B
�A�u�����v���u���������\�ʁv�̗̈悲�Ƃɕ������ē��͂���B
���w1�́u�����i�����j�ʗ̈�v�ɑ��āA�����́u�����v���܂܂��v�Z�x�ɂ͑Ή����Ă��܂����A���Ⴂ�̉����̂悤�Ɂu�����v�̓��͔͈͂��d�Ȃ�ꍇ�́A�����ʂ��Ƃɉ����ʗ̈�����ē��͂��Ă��������B
����A�w1�́u�����v�ɑ��āA�����́u�����i�����j�ʗ̈�v���܂܂��v�Z���ł��Ȃ��x�Ƃ����d�l�̂��߁A1�̉����ɑ��ĕ����́u�����i�����j�ʗ̈�v���܂܂��ꍇ�ɒ��ӊ��N�Ƃ��ĕ\�����Ă��܂��B
�������A���Ⴂ�̉����̂悤�ɉ����̓��͔͈͂��d�Ȃ�ꍇ�ł��x�����\������܂��̂ŁA�������S�̈�A���敉�S�̈�͈̔͂��K�ł���Ζ������Ă��������č\���܂���B
�������A���Ⴂ�̉����̂悤�ɉ����̓��͔͈͂��d�Ȃ�ꍇ�ł��x�����\������܂��̂ŁA�������S�̈�A���敉�S�̈�͈̔͂��K�ł���Ζ������Ă��������č\���܂���B
�����̍��W�ƁA����J�̍��W�ɔ����Ȃ��ꂪ�����Ă���ꍇ�ɕ\�������x���ł��B����J���Ĕz�u���ĉ�������邩���m�F���������B
↑�y�[�W�̐擪�֖߂�
�y�����d�v�Z�G���[�Ώ��@�z
+�@�S�ēW�J�@�b�@-�@�S�Đ܂肽����
�\���ނ̏ꍇ�A�ނ̑���������퓙�����m�F���A�g�p���Ă�����퓙���̋��x���}�X�^�[�ɓo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
�S�p���p�������Ă��邩���A���m�F���������B
�S�p���p�������Ă��邩���A���m�F���������B
�lj������z�d�A�lj��W���d�����ˍޏ�ɔz�u����Ă��Ȃ����ɕ\������܂��B�lj��d�̈ʒu���m�F���Ă��������B
�d��������Ȃ����ߏ��d�E���ύډd�E�ljd�E�����d���ݒ�ł��Ȃ���Ԃł��B
CAD��ʂ́u�G���[�\���v�u���S�̈�`�F�b�N�v�⒠�[�́u�d���S�}�v�ɂāA�ǂ��̉d���E���Ă��Ȃ��̂��ꏊ���m�F������ʼn��L�̎������`�F�b�N���Ă��������B
�m�F�����P�ˁy�����S�̋��ʁz
�e���ނ̒[�_�������Ă��邩�m�F���Ă��������B
��b�����m�A��b���ƃX���u�A�y��Ɗ�b���A���ˍޓ��m�A�����Ƌ��ؓ��A�v�f�̒[�_�������Ă��Ȃ����ɂ̓G���[���\�������ꍇ������܂��B
NSC�ł́A���������f��������ɂ�����A�z�u�_���n�_�E�I�_�Ƃ��ă��f�������Ă��܂��B�e�K�E�e�v�f�̔z�u�_�����킹����ŁA�[����l�E�I�t�Z�b�g���Œ��������Ē����悤���肢�v���܂��B
�i�[����l�E�I�t�Z�b�g�͌v�Z�ɂ͉e���͂���܂���B�j
�m�F�����Q�ˁy�㕨(����)�̏ꍇ�z
�����Ɖ��ˍނ̍��፷����v���Ă��邩�m�F���Ă��������B
�u�����v�ƍ��፷�������Ă��鉡�ˍނ̂݉����d�S����d�l�ƂȂ��Ă��邽�߁A���ˍނ̍��፷���m�F���Ă��������B
�܂��A�\���v�Z�_�~�[���ɂ��Ă����l�ł��邽�߁A�_�~�[���̍��፷���m�F���Ă��������B
�m�F�����R�ˁy�㕨�̏ꍇ�z
�����\�ʗ̈�E���g�̓��͏��m�F���Ă��������B
�������\�ʗ̈�̊O������́A�K����������悤�ɂ��Ă��������B
�܂��A���፷���Q�Ƃ���d�l�Ƃ��Ă��邽�߁A�������\�ʗ̈�̃��x���������͈͓̔��Ɏ��܂��Ă��邩�ۂ����m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�m�F�����S�ˁy��b�̏ꍇ�z
�X���u�̊O���Ɋ�b�������邩�m�F���Ă��������B
��b�̕��ŕ\������铖�Y�G���[�́A�\���ރ_�~�[�ނł̓G���[�������ł��܂���B
�ڍ����̗�ł́A�x�^��b�X���u�̊O������Ɋ�b���������͈͂����邽�߁A�X���u����b���ɉd�𗬂����Ƃ��ł����ɃG���[���o�Ă��܂��B���̂��߁A�u�x�^��b�����v���u�n�����v����͂��Ă���������G���[�͉����ł��܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
CAD��ʂ́u�G���[�\���v�u���S�̈�`�F�b�N�v�⒠�[�́u�d���S�}�v�ɂāA�ǂ��̉d���E���Ă��Ȃ��̂��ꏊ���m�F������ʼn��L�̎������`�F�b�N���Ă��������B
�m�F�����P�ˁy�����S�̋��ʁz
�e���ނ̒[�_�������Ă��邩�m�F���Ă��������B
��b�����m�A��b���ƃX���u�A�y��Ɗ�b���A���ˍޓ��m�A�����Ƌ��ؓ��A�v�f�̒[�_�������Ă��Ȃ����ɂ̓G���[���\�������ꍇ������܂��B
NSC�ł́A���������f��������ɂ�����A�z�u�_���n�_�E�I�_�Ƃ��ă��f�������Ă��܂��B�e�K�E�e�v�f�̔z�u�_�����킹����ŁA�[����l�E�I�t�Z�b�g���Œ��������Ē����悤���肢�v���܂��B
�i�[����l�E�I�t�Z�b�g�͌v�Z�ɂ͉e���͂���܂���B�j
�m�F�����Q�ˁy�㕨(����)�̏ꍇ�z
�����Ɖ��ˍނ̍��፷����v���Ă��邩�m�F���Ă��������B
�u�����v�ƍ��፷�������Ă��鉡�ˍނ̂݉����d�S����d�l�ƂȂ��Ă��邽�߁A���ˍނ̍��፷���m�F���Ă��������B
�܂��A�\���v�Z�_�~�[���ɂ��Ă����l�ł��邽�߁A�_�~�[���̍��፷���m�F���Ă��������B
�m�F�����R�ˁy�㕨�̏ꍇ�z
�����\�ʗ̈�E���g�̓��͏��m�F���Ă��������B
�������\�ʗ̈�̊O������́A�K����������悤�ɂ��Ă��������B
�܂��A���፷���Q�Ƃ���d�l�Ƃ��Ă��邽�߁A�������\�ʗ̈�̃��x���������͈͓̔��Ɏ��܂��Ă��邩�ۂ����m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)�m�F�����S�ˁy��b�̏ꍇ�z
�X���u�̊O���Ɋ�b�������邩�m�F���Ă��������B
��b�̕��ŕ\������铖�Y�G���[�́A�\���ރ_�~�[�ނł̓G���[�������ł��܂���B
�ڍ����̗�ł́A�x�^��b�X���u�̊O������Ɋ�b���������͈͂����邽�߁A�X���u����b���ɉd�𗬂����Ƃ��ł����ɃG���[���o�Ă��܂��B���̂��߁A�u�x�^��b�����v���u�n�����v����͂��Ă���������G���[�͉����ł��܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
��{�I�ɂ́u���S�̈悪�o�^�ł��܂���ł����B�i���� m2�j�v�̃G���[�Ɠ��l�̃`�F�b�N���s���Ă��������B
�m�F�����P�ˁy�㕨(����)�̏ꍇ�z
�u�����v�Ɓu�����ʗ̈�v�̓��͏����m�F���������B
�w1�́u�����v�ɑ��āA�����́u�����ʗ̈�v���܂܂��v�Z�x���ł��Ȃ��d�l�̂��߁A�P�́u�����v�ɑ��ĂP�́u�����ʗ̈�v�ɂȂ�悤�ɓ��͂��C�����Ă��������B
���w1�́u�����ʗ̈�v�ɑ��āA�����́u�����v���܂܂��v�Z�x�͉\�ł��B
���Ⴂ�̉����̂悤�Ɂu�����v�̓��͔͈͂��d�Ȃ�ꍇ�́A�����ʂ��Ƃɉ����ʗ̈��������ŁA�����Ɖ����ʗ̈�̔z�u���C���𑵂��Ă��������B
�m�F�����Q�ˁy�㕨�̏ꍇ�z
���ނ��v�Z�ΏۊO�ł��邩�ǂ������m�F���������B
���⒌���v�Z�ΏۊO�ɂȂ��Ă��邽�߁A�d�̓`�B��������邱�Ƃ��ł����G���[���o��ꍇ������܂��B�v�Z�Ώ�/�v�Z�ΏۊO�̐ݒ肪�K�ł��邩���m�F���������B
�m�F�����P�ˁy�㕨(����)�̏ꍇ�z
�u�����v�Ɓu�����ʗ̈�v�̓��͏����m�F���������B
�w1�́u�����v�ɑ��āA�����́u�����ʗ̈�v���܂܂��v�Z�x���ł��Ȃ��d�l�̂��߁A�P�́u�����v�ɑ��ĂP�́u�����ʗ̈�v�ɂȂ�悤�ɓ��͂��C�����Ă��������B
���w1�́u�����ʗ̈�v�ɑ��āA�����́u�����v���܂܂��v�Z�x�͉\�ł��B
���Ⴂ�̉����̂悤�Ɂu�����v�̓��͔͈͂��d�Ȃ�ꍇ�́A�����ʂ��Ƃɉ����ʗ̈��������ŁA�����Ɖ����ʗ̈�̔z�u���C���𑵂��Ă��������B
�m�F�����Q�ˁy�㕨�̏ꍇ�z
���ނ��v�Z�ΏۊO�ł��邩�ǂ������m�F���������B
���⒌���v�Z�ΏۊO�ɂȂ��Ă��邽�߁A�d�̓`�B��������邱�Ƃ��ł����G���[���o��ꍇ������܂��B�v�Z�Ώ�/�v�Z�ΏۊO�̐ݒ肪�K�ł��邩���m�F���������B
��b�J���̒���ɒ����z�u����Ă���ꍇ�ɕ\�������G���[�ł��B���ނ̔[�܂肪���������m�F���Ă��������B
�u�A�������v�͈͓̔��ɂ����b���̑����́u�Z�����́v�̐ݒ肪�����Ă��Ȃ��ꍇ�ɕ\�������G���[�ł��B�u�Z�����́v�̐ݒ肪�S�đ����Ă��邩�m�F���Ă��������B
���H�������s���Ɂu�\���v�Z�}�X�^�[�^�f�ʌ����^�[���d���^�u�v�̐ݒ���݂Ē[���d���̗L���f�ʐς��Z�o���Ă���܂��B�����͂���͂��Ȃ̂Ɏd���̗L���ʐς��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���ӊ��N�Ƃ��ăG���[��\������悤�ɂ��Ă��܂��̂ŁA�}�X�^�[���K�ɐݒ肳��Ă��邩���m�F���������B
�������A����̓}�X�^�[�ݒ�菇���ɋL�ڂ̂���d�������f�ʌ����}�X�^�[�Ƃ̘A�g�ɑΉ����Ă��Ȃ����߁A�}�X�^�[��ݒ肵�Ă��d���ɂ���Ă̓G���[���\�������ꍇ������܂��B
���̏ꍇ�́A���萔�ł����ޑ����̍\���v�Z�^�u�̒[���d�����ŗL���ސ��A�L���ʐς�����͂Őݒ肵�Ă��Ή������肢�v���܂��B
�Ȃ��A�u�d���L���ʐς����ݒ�ł��B�v�̃G���[�ɂ��ẮA�\���v�Z�̃G���[�̂��߁A���H�f�[�^�̏o�͂ɂ͉e������܂���B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�������A����̓}�X�^�[�ݒ�菇���ɋL�ڂ̂���d�������f�ʌ����}�X�^�[�Ƃ̘A�g�ɑΉ����Ă��Ȃ����߁A�}�X�^�[��ݒ肵�Ă��d���ɂ���Ă̓G���[���\�������ꍇ������܂��B
���̏ꍇ�́A���萔�ł����ޑ����̍\���v�Z�^�u�̒[���d�����ŗL���ސ��A�L���ʐς�����͂Őݒ肵�Ă��Ή������肢�v���܂��B
�Ȃ��A�u�d���L���ʐς����ݒ�ł��B�v�̃G���[�ɂ��ẮA�\���v�Z�̃G���[�̂��߁A���H�f�[�^�̏o�͂ɂ͉e������܂���B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�����ϗ͂��P���ݒ肵�Ă��Ȃ����ɕ\������܂��B
�����ϗ͂�V�K�ݒ肵�Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�����ϗ͂�V�K�ݒ肵�Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�����ϗ͂̓o�^�p�^�[�����s�����Ă��鎞�ɕ\������܂��B
�S�Ă̏����œo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�S�Ă̏����œo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�����ϗ͂̓o�^�p�^�[�����s�����Ă��鎞�ɕ\������܂��B
�S�Ă̏����œo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�S�Ă̏����œo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�^�����ҏW�v�ɂ����āA(���ނ�)����⑊��ސ��̏������������ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�^�����ҏW�v�ɂ����āA(���ނ�)����⑊��ސ��̏������������ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�\���v�Z�ݒ�^�ڍ����v�́u�t����f�̌����v�Ƀ`�F�b�N��t�����ꍇ�ɕ\������܂��B
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�t����f�ϗ͂��o�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�t����f�ϗ͂��o�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�}�X�^�[�ݒ�菇�����Q�l�ɁA�uXstar�œ��͂��������}�X�^�[�v�Ɓu�\���v�Z�p�̋������x�}�X�^�[�v�̖��̂���v���Ă��邩���m�F���������B
��v���Ă��Ȃ��ꍇ�͋������x���A�g����܂���B
�܂��A�Αł������Ɋւ��Ă͉��L�̂R�_�̖��̂������Ă��邱�Ƃ����m�F���������B
�E���}��ɓ��͂��Ă���Αł����̎���
�@���u���퓙���}�X�^�[�^����v�ɓo�^���Ă������̑����Łu�S�A���O���v�Ƀ`�F�b�N�������Ă�����킪�Ώۂł��B
�E�u�����ݒ�^�����ݒ�^�d�l�ؑց^�S�A���O���ΑŁv�œo�^���Ă����������
�E�u�������x�}�X�^�[�^�⋭�����^�Αŋ����v�̋�������
��v���Ă��Ȃ��ꍇ�͋������x���A�g����܂���B
�܂��A�Αł������Ɋւ��Ă͉��L�̂R�_�̖��̂������Ă��邱�Ƃ����m�F���������B
�E���}��ɓ��͂��Ă���Αł����̎���
�@���u���퓙���}�X�^�[�^����v�ɓo�^���Ă������̑����Łu�S�A���O���v�Ƀ`�F�b�N�������Ă�����킪�Ώۂł��B
�E�u�����ݒ�^�����ݒ�^�d�l�ؑց^�S�A���O���ΑŁv�œo�^���Ă����������
�E�u�������x�}�X�^�[�^�⋭�����^�Αŋ����v�̋�������
↑�y�[�W�̐擪�֖߂�
�yNSC-�ǗʁE�ΐS���v�Z�z
+�@�S�ēW�J�@�b�@-�@�S�Đ܂肽����
�ϗ͕Ǒ����́u�g�����v�^�u�̏ヌ�x���E�����x���ڕύX���邱�ƂŒ����\�ł��B
�u�����ݒ�^�\���v�Z�ݒ�^�n����v�^�u�́h���ʐςɏ悸��l�icm/�u�j�h�̔C�Ӓl�w��ŁA���̏��a�u�R�D���̏��a�ʂɒ��̕��S�\�ʐς����߂�v��I�����Ă���̂ɁA�u���S�\�ʐρi�u�j�v���ݒ肳��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���u���S�\�ʐρi�u�j�v�ɂ́A�\�v�Z�c�[���Ŏ����ꂽ���S�\�ʐς�ݒ肵�Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
���u���S�\�ʐρi�u�j�v�ɂ́A�\�v�Z�c�[���Ŏ����ꂽ���S�\�ʐς�ݒ肵�Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����ݒ�^�����ݒ�^���W���[���v�́u�I�t�Z�b�g�v��ݒ肵�č\���v�Z���ēx���s��A���[�̏o�͂����肢�v���܂��B
����ANSC�ł͏Z�Z���^�[�̕\�v�Z�c�[���ɍ��킹�ČW���������v�Z����d�l�ƂȂ��Ă���A�k�C���ł̕\�v�Z�c�[���͍l������Ă���܂���B
���̂��߁ANSC-�ǗʁE�ΐS���v�Z�ɂ����Ă͐�~�߂̐ݒ���܂߂āA�ϐ�d�͌W���Z�o�ɍl�����ꂸ�A���[�́u1-2.�����T�v�v�݂̂ɕ\�����Ă���܂��B
�i���\�]���v�Z�A�����d�v�Z���[�h�̏ꍇ�́A�ϐ�d�͍l������܂��j
�ϐ�d���l�����ČW�����Z�o�������ꍇ�́A�k�C���ŕ\�v�Z�c�[���ŌW�����Z�o��Ɂu�����ݒ�^�\���v�Z�ݒ�^�n����v�^�u�́h���ʐςɏ悸��l�icm/�u�j�h�ɂāA�u�C�Ӓl�w��v��I�����Ē����悤���肢�v���܂��B
���̂��߁ANSC-�ǗʁE�ΐS���v�Z�ɂ����Ă͐�~�߂̐ݒ���܂߂āA�ϐ�d�͌W���Z�o�ɍl�����ꂸ�A���[�́u1-2.�����T�v�v�݂̂ɕ\�����Ă���܂��B
�i���\�]���v�Z�A�����d�v�Z���[�h�̏ꍇ�́A�ϐ�d�͍l������܂��j
�ϐ�d���l�����ČW�����Z�o�������ꍇ�́A�k�C���ŕ\�v�Z�c�[���ŌW�����Z�o��Ɂu�����ݒ�^�\���v�Z�ݒ�^�n����v�^�u�́h���ʐςɏ悸��l�icm/�u�j�h�ɂāA�u�C�Ӓl�w��v��I�����Ē����悤���肢�v���܂��B
���̑����ŔC�ӂɕҏW���Ă��Ȃ��ꍇ�́A���t�������\������܂��B
�������͂���Ă��Ȃ��ꍇ�́A�u�K���|�Œ�l�̗����v���\������܂��B
�Œ�l�̗����́u�����ݒ�^�\���v�Z�ݒ�^�v�Z�����v�^�u�́h�����a�Z��p�����h���Q�Ƃ��܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�������͂���Ă��Ȃ��ꍇ�́A�u�K���|�Œ�l�̗����v���\������܂��B
�Œ�l�̗����́u�����ݒ�^�\���v�Z�ݒ�^�v�Z�����v�^�u�́h�����a�Z��p�����h���Q�Ƃ��܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)↑�y�[�W�̐擪�֖߂�
�yNSC-���\�]���v�Z�z
+�@�S�ēW�J�@�b�@-�@�S�Đ܂肽����
�u�Αŗ̈�v�����͂���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�Αŗ̈�v�����͂���Ă���ꍇ�A�̈�ň͂����͈͂ʼnΑł��̕��S�ʐς��v�Z����܂��B
�ǐ����ƂɌ�������ꍇ�́A�Αł��̈��z�u�����ɁA�u�����ݒ�^���͐ݒ�^���͕W���l�ݒ�^��ʐݒ�2�v�ɂĐ����\�ʂ̉Αł��̎d�l��ݒ肵�Ē����܂��ƁA�ǐ��ԂŌ�������܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�ǐ����ƂɌ�������ꍇ�́A�Αł��̈��z�u�����ɁA�u�����ݒ�^���͐ݒ�^���͕W���l�ݒ�^��ʐݒ�2�v�ɂĐ����\�ʂ̉Αł��̎d�l��ݒ肵�Ē����܂��ƁA�ǐ��ԂŌ�������܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�������ō��Z�ł���ǐ�����������ꍇ�ɂ́A�C�ӂō��Z����������w�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
�u�\���v�Z�^�ϗ͕ǐ����Z�v��I�����A�P�_�ڂō��Z����ǐ����w��A�Q�_�ڂō��Z��̕ǐ����w�肵�܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�\���v�Z�^�ϗ͕ǐ����Z�v��I�����A�P�_�ڂō��Z����ǐ����w��A�Q�_�ڂō��Z��̕ǐ����w�肵�܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�ؑ����g�H�@�Z��̋��e���͓x�v 2017�N�x��(�O���[�{)�̖{���Ɠ��l�Ɂu�y��̂߂荞�������ȊO�́A�Z�����͂ɋȂ��߂����ʂ�"�l�����Ȃ�"�v�Œ�Ƃ��Ă��܂������A�Z�Z���^�[�z�[���y�[�W��2017�N�ŃO���[�{��Q&A��54�Ԃ̓��e�Łu�Z�����͂ɂ����Ă��Ȃ��߂����ʂ͊��҂ł���v�ƋL�ڂ����邽�߁A�u�Ȃ��߂��W����"�l������"�v���I���ł���悤�ɂ��܂����B
�ǂ����I�����邩�͐v�Ҕ��f�ƂȂ�܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�ǂ����I�����邩�͐v�Ҕ��f�ƂȂ�܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)↑�y�[�W�̐擪�֖߂�
�yNSC-�m�l�v�Z�z
+�@�S�ēW�J�@�b�@-�@�S�Đ܂肽����
�uN�l�v�Z�V�[�g����v�́u����ݒ�v�{�^���Œ������r����̕\���ݒ肪�\�ł��B�\���v�Z�}�X�^�[�́u����ݒ�v�ŁA�V�K�����̍ۂ̏����l�̐ݒ�ɂ��Ή����Ă���܂��B
�m�F�����P�ˁu�⏕�^�}�X�^�[�ҏW�^�\���v�Z�}�X�^�[�^�������x�v�̊Y���d�l�́u�ϗ͐ݒ�^�����L���^�u�v���ݒ肳��Ă��邩���m�F���������B
�m�F�����Q�ˁu�\���v�Z�ݒ�^�v�d�^�u�v�́u�����H�@���x�v�Ɓu�⋭�������x�v�̐ݒ�����m�F���������B
�����H�@�̕����ł���u�����H�@���x�v�A�ݗ��H�@�̕����ł���u�⋭�������x�v�Őݒ肷�邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���܂��B
�u�����H�@���x�v�Ɓu�⋭�������x�v�̗�����I�����Ă���ꍇ�A�u�����H�@���x�v�̐ݒ肪�D�悳��܂��̂ŁA�ݗ��H�@�̏ꍇ�́u�����H�@���x�v���ɂ��Ă��������B
�����H�@�ƍݗ��H�@�����݂��Ăǂ�����}�X�^�[��A�g����ꍇ�́A�u�����H�@���x�v�őI�����Ă���������x�}�X�^�[�́u�����L���^�u�v���ݒ肪�K�v�ł��B
�m�F�����Q�ˁu�\���v�Z�ݒ�^�v�d�^�u�v�́u�����H�@���x�v�Ɓu�⋭�������x�v�̐ݒ�����m�F���������B
�����H�@�̕����ł���u�����H�@���x�v�A�ݗ��H�@�̕����ł���u�⋭�������x�v�Őݒ肷�邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���܂��B
�u�����H�@���x�v�Ɓu�⋭�������x�v�̗�����I�����Ă���ꍇ�A�u�����H�@���x�v�̐ݒ肪�D�悳��܂��̂ŁA�ݗ��H�@�̏ꍇ�́u�����H�@���x�v���ɂ��Ă��������B
�����H�@�ƍݗ��H�@�����݂��Ăǂ�����}�X�^�[��A�g����ꍇ�́A�u�����H�@���x�v�őI�����Ă���������x�}�X�^�[�́u�����L���^�u�v���ݒ肪�K�v�ł��B
�\���v�Z���[�h�Œ��̑������N�����āA���������́u�\���v�Z�v�^�u�́u�v�Z���ʁv���N���b�N���܂��B
�u��ԁv�̘g�����_�u���N���b�N����ƁA�ҏW��ʂ��\������ďo�����ʏ킩��ύX���邱�Ƃ��ł��܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u��ԁv�̘g�����_�u���N���b�N����ƁA�ҏW��ʂ��\������ďo�����ʏ킩��ύX���邱�Ƃ��ł��܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�\���v�Z���[�h�Œ��̑������N�����āA���������́u�\���v�Z�v�^�u�́u�v�Z���ʁv���N���b�N���܂��B
�u���������v�܂��́u���r�����v�̘g�����_�u���N���b�N����Ɓu�����ҏW�v��ʂ��\������܂��̂ŁA�C�ӂ̋�����I�����čēx�v�Z�����s���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u���������v�܂��́u���r�����v�̘g�����_�u���N���b�N����Ɓu�����ҏW�v��ʂ��\������܂��̂ŁA�C�ӂ̋�����I�����čēx�v�Z�����s���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�⏕�^�}�X�^�[�ҏW�^�\���v�Z�}�X�^�[�v�̋������x�}�X�^�[����U�ۑ����Ȃ����āACAD���ċN�����Ă��������B
����A���U�ǂ̕\���͌Œ�ƂȂ��Ă���ύX���邱�Ƃ��ł��܂���B
���U�Ǖ\���̕����ɂ��܂��Ă͏ڍ��������m�F���������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
���U�Ǖ\���̕����ɂ��܂��Ă͏ڍ��������m�F���������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�؈�ϗ͕ǂ̍�����3.2�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�V��ł́A�؈�ϗ͕ǂ̍�����3.2m����ꍇ�͕ǔ{���ɒጸ�W�����悶��悤�ɂȂ��Ă���܂��̂ŁANSC�ł����̂悤�Ɍv�Z���Ă���܂��B
�؈ፂ���ɂ��ጸ�W�� ����3.5�~�ǒ��^���V�[����
(1����ꍇ�ɂ� ��=1�Ƃ��Čv�Z)
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�V��ł́A�؈�ϗ͕ǂ̍�����3.2m����ꍇ�͕ǔ{���ɒጸ�W�����悶��悤�ɂȂ��Ă���܂��̂ŁANSC�ł����̂悤�Ɍv�Z���Ă���܂��B
�؈ፂ���ɂ��ጸ�W�� ����3.5�~�ǒ��^���V�[����
(1����ꍇ�ɂ� ��=1�Ƃ��Čv�Z)
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
NSC�ł́A���̑�����ʂ́������̉d�̓v���X�A�������̉d�̓}�C�i�X�ŕ\������܂��B
���̂��߁AN�l�v�Z�V�[�g��\���v�Z���ʈꗗ�ƁA���̑�����ʂƂŃv���X�A�}�C�i�X���t�ŕ\������܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
���̂��߁AN�l�v�Z�V�[�g��\���v�Z���ʈꗗ�ƁA���̑�����ʂƂŃv���X�A�}�C�i�X���t�ŕ\������܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)↑�y�[�W�̐擪�֖߂�
�yNSC-���e���͓x�v�Z�i���[�g1�j�z
+�@�S�ēW�J�@�b�@-�@�S�Đ܂肽����
�u�����ݒ�^�����ݒ�^�\���ݒ�v�́u��ʐݒ�v�^�u�ŁA���ڍ����u�m�l�v��I�����Ă��������ƁACAD��ʂŒ��Ɉ����͂��\������܂��B
�v�Z���u�������r�����z�u�}�v�̒��Ɉ����͂�\������ꍇ�́A�\���v�Z����ݒ��ʂ́u����ݒ�v�ɂāA�u�����z�u�}�Ɉ����͂�\���v�Ƀ`�F�b�N��t���ďo�͂��Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�v�Z���u�������r�����z�u�}�v�̒��Ɉ����͂�\������ꍇ�́A�\���v�Z����ݒ��ʂ́u����ݒ�v�ɂāA�u�����z�u�}�Ɉ����͂�\���v�Ƀ`�F�b�N��t���ďo�͂��Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
����ANSC�ł̓]�[�����Ƃ̌v�Z�ɂ͑Ή��ł��Ă��܂���B
�����f�[�^���]�[�����ɕ����Čv�Z�����肢�������܂��B
�����f�[�^���]�[�����ɕ����Čv�Z�����肢�������܂��B
�u�\���v�Z�ݒ�^���t�ʐρv�̌��t�쐬�`��̐ݒ�����m�F���������B
�u�S�ĕǁv��I�����Ă���ꍇ�́A���������Ă���Ό��t�`����ł��܂����A�u�����ƕǂ���v��I�����Ă���ꍇ�́A���t�`��̐����̕������Q�Ƃ��Č`������Ă��܂��B�C�������`����ēx�A���v���ƂȂ�悤�ɐ������͂��Ă��������ƗΐF�̌��t�`�\�������悤�ɂȂ�܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�S�ĕǁv��I�����Ă���ꍇ�́A���������Ă���Ό��t�`����ł��܂����A�u�����ƕǂ���v��I�����Ă���ꍇ�́A���t�`��̐����̕������Q�Ƃ��Č`������Ă��܂��B�C�������`����ēx�A���v���ƂȂ�悤�ɐ������͂��Ă��������ƗΐF�̌��t�`�\�������悤�ɂȂ�܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)↑�y�[�W�̐擪�֖߂�
�yNSC-���e���͓x�v�Z�i���[�g1�j�G���[�Ώ��@�z
+�@�S�ēW�J�@�b�@-�@�S�Đ܂肽����
�\���ނ̏ꍇ�A�ނ̑���������퓙�����m�F���A�g�p���Ă�����퓙���̋��x���}�X�^�[�ɓo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
�[���ނ̏ꍇ�A�u�����d�l�^�ސݒ�^�[���ށv�ɐݒ肵�Ă�����퓙���̋��x���}�X�^�[�ɓo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
�S�p���p�������Ă��邩���A���m�F���������B
�[���ނ̏ꍇ�A�u�����d�l�^�ސݒ�^�[���ށv�ɐݒ肵�Ă�����퓙���̋��x���}�X�^�[�ɓo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
�S�p���p�������Ă��邩���A���m�F���������B
�u�\���v�Z�ݒ�^�Q�����ށ^���̌����v�ɐݒ肵�������ގd�l�̕ҏW��ʂ��J���A�u��������ꉮ�܂ł̋����v���ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
�lj������z�d�A�lj��W���d�����ˍޏ�ɔz�u����Ă��Ȃ����ɕ\������܂��B�lj��d�̈ʒu���m�F���Ă��������B
�d��������Ȃ����ߏ��d�E���ύډd�E�ljd�E�����d���ݒ�ł��Ȃ���Ԃł��B
CAD��ʂ́u�G���[�\���v�u���S�̈�`�F�b�N�v�⒠�[�́u�d���S�}�v�ɂāA�ǂ��̉d���E���Ă��Ȃ��̂��ꏊ���m�F������ʼn��L�̎������`�F�b�N���Ă��������B
�m�F�����P�ˁy�����S�̋��ʁz
�e���ނ̒[�_�������Ă��邩�m�F���Ă��������B
��b�����m�A��b���ƃX���u�A�y��Ɗ�b���A���ˍޓ��m�A�����Ƌ��ؓ��A�v�f�̒[�_�������Ă��Ȃ����ɂ̓G���[���\�������ꍇ������܂��B
NSC�ł́A���������f��������ɂ�����A�z�u�_���n�_�E�I�_�Ƃ��ă��f�������Ă��܂��B�e�K�E�e�v�f�̔z�u�_�����킹����ŁA�[����l�E�I�t�Z�b�g���Œ��������Ē����悤���肢�v���܂��B
�i�[����l�E�I�t�Z�b�g�͌v�Z�ɂ͉e���͂���܂���B�j
�m�F�����Q�ˁy�㕨(����)�̏ꍇ�z
�����Ɖ��ˍނ̍��፷����v���Ă��邩�m�F���Ă��������B
�u�����v�ƍ��፷�������Ă��鉡�ˍނ̂݉����d�S����d�l�ƂȂ��Ă��邽�߁A���ˍނ̍��፷���m�F���Ă��������B
�܂��A�\���v�Z�_�~�[���ɂ��Ă����l�ł��邽�߁A�_�~�[���̍��፷���m�F���Ă��������B
�m�F�����R�ˁy�㕨�̏ꍇ�z
�����\�ʗ̈�E���g�̓��͏��m�F���Ă��������B
�������\�ʗ̈�̊O������́A�K����������悤�ɂ��Ă��������B
�܂��A���፷���Q�Ƃ���d�l�Ƃ��Ă��邽�߁A�������\�ʗ̈�̃��x���������͈͓̔��Ɏ��܂��Ă��邩�ۂ����m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�m�F�����S�ˁy��b�̏ꍇ�z
�X���u�̊O���Ɋ�b�������邩�m�F���Ă��������B
��b�̕��ŕ\������铖�Y�G���[�́A�\���ރ_�~�[�ނł̓G���[�������ł��܂���B
�ڍ����̗�ł́A�x�^��b�X���u�̊O������Ɋ�b���������͈͂����邽�߁A�X���u����b���ɉd�𗬂����Ƃ��ł����ɃG���[���o�Ă��܂��B���̂��߁A�u�x�^��b�����v���u�n�����v����͂��Ă���������G���[�͉����ł��܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
CAD��ʂ́u�G���[�\���v�u���S�̈�`�F�b�N�v�⒠�[�́u�d���S�}�v�ɂāA�ǂ��̉d���E���Ă��Ȃ��̂��ꏊ���m�F������ʼn��L�̎������`�F�b�N���Ă��������B
�m�F�����P�ˁy�����S�̋��ʁz
�e���ނ̒[�_�������Ă��邩�m�F���Ă��������B
��b�����m�A��b���ƃX���u�A�y��Ɗ�b���A���ˍޓ��m�A�����Ƌ��ؓ��A�v�f�̒[�_�������Ă��Ȃ����ɂ̓G���[���\�������ꍇ������܂��B
NSC�ł́A���������f��������ɂ�����A�z�u�_���n�_�E�I�_�Ƃ��ă��f�������Ă��܂��B�e�K�E�e�v�f�̔z�u�_�����킹����ŁA�[����l�E�I�t�Z�b�g���Œ��������Ē����悤���肢�v���܂��B
�i�[����l�E�I�t�Z�b�g�͌v�Z�ɂ͉e���͂���܂���B�j
�m�F�����Q�ˁy�㕨(����)�̏ꍇ�z
�����Ɖ��ˍނ̍��፷����v���Ă��邩�m�F���Ă��������B
�u�����v�ƍ��፷�������Ă��鉡�ˍނ̂݉����d�S����d�l�ƂȂ��Ă��邽�߁A���ˍނ̍��፷���m�F���Ă��������B
�܂��A�\���v�Z�_�~�[���ɂ��Ă����l�ł��邽�߁A�_�~�[���̍��፷���m�F���Ă��������B
�m�F�����R�ˁy�㕨�̏ꍇ�z
�����\�ʗ̈�E���g�̓��͏��m�F���Ă��������B
�������\�ʗ̈�̊O������́A�K����������悤�ɂ��Ă��������B
�܂��A���፷���Q�Ƃ���d�l�Ƃ��Ă��邽�߁A�������\�ʗ̈�̃��x���������͈͓̔��Ɏ��܂��Ă��邩�ۂ����m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)�m�F�����S�ˁy��b�̏ꍇ�z
�X���u�̊O���Ɋ�b�������邩�m�F���Ă��������B
��b�̕��ŕ\������铖�Y�G���[�́A�\���ރ_�~�[�ނł̓G���[�������ł��܂���B
�ڍ����̗�ł́A�x�^��b�X���u�̊O������Ɋ�b���������͈͂����邽�߁A�X���u����b���ɉd�𗬂����Ƃ��ł����ɃG���[���o�Ă��܂��B���̂��߁A�u�x�^��b�����v���u�n�����v����͂��Ă���������G���[�͉����ł��܂��B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
��{�I�ɂ́u���S�̈悪�o�^�ł��܂���ł����B�i���� m2�j�v�̃G���[�Ɠ��l�̃`�F�b�N���s���Ă��������B
�m�F�����P�ˁy�㕨(����)�̏ꍇ�z
�u�����v�Ɓu�����ʗ̈�v�̓��͏����m�F���������B
�w1�́u�����v�ɑ��āA�����́u�����ʗ̈�v���܂܂��v�Z�x���ł��Ȃ��d�l�̂��߁A�P�́u�����v�ɑ��ĂP�́u�����ʗ̈�v�ɂȂ�悤�ɓ��͂��C�����Ă��������B
���w1�́u�����ʗ̈�v�ɑ��āA�����́u�����v���܂܂��v�Z�x�͉\�ł��B
���Ⴂ�̉����̂悤�Ɂu�����v�̓��͔͈͂��d�Ȃ�ꍇ�́A�����ʂ��Ƃɉ����ʗ̈��������ŁA�����Ɖ����ʗ̈�̔z�u���C���𑵂��Ă��������B
�m�F����2�ˁy�㕨�̏ꍇ�z
���ނ��v�Z�ΏۊO�ł��邩�ǂ������m�F���������B
���⒌���v�Z�ΏۊO�ɂȂ��Ă��邽�߁A�d�̓`�B��������邱�Ƃ��ł����G���[���o��ꍇ������܂��B�v�Z�Ώ�/�v�Z�ΏۊO�̐ݒ肪�K�ł��邩���m�F���������B
�m�F�����P�ˁy�㕨(����)�̏ꍇ�z
�u�����v�Ɓu�����ʗ̈�v�̓��͏����m�F���������B
�w1�́u�����v�ɑ��āA�����́u�����ʗ̈�v���܂܂��v�Z�x���ł��Ȃ��d�l�̂��߁A�P�́u�����v�ɑ��ĂP�́u�����ʗ̈�v�ɂȂ�悤�ɓ��͂��C�����Ă��������B
���w1�́u�����ʗ̈�v�ɑ��āA�����́u�����v���܂܂��v�Z�x�͉\�ł��B
���Ⴂ�̉����̂悤�Ɂu�����v�̓��͔͈͂��d�Ȃ�ꍇ�́A�����ʂ��Ƃɉ����ʗ̈��������ŁA�����Ɖ����ʗ̈�̔z�u���C���𑵂��Ă��������B
�m�F����2�ˁy�㕨�̏ꍇ�z
���ނ��v�Z�ΏۊO�ł��邩�ǂ������m�F���������B
���⒌���v�Z�ΏۊO�ɂȂ��Ă��邽�߁A�d�̓`�B��������邱�Ƃ��ł����G���[���o��ꍇ������܂��B�v�Z�Ώ�/�v�Z�ΏۊO�̐ݒ肪�K�ł��邩���m�F���������B
���H�������s���Ɂu�\���v�Z�}�X�^�[�^�f�ʌ����^�[���d���^�u�v�̐ݒ���݂Ē[���d���̗L���f�ʐς��Z�o���Ă���܂��B�����͂���͂��Ȃ̂Ɏd���̗L���ʐς��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���ӊ��N�Ƃ��ăG���[��\������悤�ɂ��Ă��܂��̂ŁA�}�X�^�[���K�ɐݒ肳��Ă��邩���m�F���������B
�������A����̓}�X�^�[�ݒ�菇���ɋL�ڂ̂���d�������f�ʌ����}�X�^�[�Ƃ̘A�g�ɑΉ����Ă��Ȃ����߁A�}�X�^�[��ݒ肵�Ă��d���ɂ���Ă̓G���[���\�������ꍇ������܂��B
���̏ꍇ�́A���萔�ł����ޑ����̍\���v�Z�^�u�̒[���d�����ŗL���ސ��A�L���ʐς�����͂Őݒ肵�Ă��Ή������肢�v���܂��B
�Ȃ��A�u�d���L���ʐς����ݒ�ł��B�v�̃G���[�ɂ��ẮA�\���v�Z�̃G���[�̂��߁A���H�f�[�^�̏o�͂ɂ͉e������܂���B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�������A����̓}�X�^�[�ݒ�菇���ɋL�ڂ̂���d�������f�ʌ����}�X�^�[�Ƃ̘A�g�ɑΉ����Ă��Ȃ����߁A�}�X�^�[��ݒ肵�Ă��d���ɂ���Ă̓G���[���\�������ꍇ������܂��B
���̏ꍇ�́A���萔�ł����ޑ����̍\���v�Z�^�u�̒[���d�����ŗL���ސ��A�L���ʐς�����͂Őݒ肵�Ă��Ή������肢�v���܂��B
�Ȃ��A�u�d���L���ʐς����ݒ�ł��B�v�̃G���[�ɂ��ẮA�\���v�Z�̃G���[�̂��߁A���H�f�[�^�̏o�͂ɂ͉e������܂���B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�Y���ӏ��Ɉ�����������͂��Ă��������B
�y���ڍ����z
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�����ϗ͂��P���ݒ肵�Ă��Ȃ����ɕ\������܂��B�����ϗ͂�V�K�ݒ肵�Ă��������B
�y�������z
�u�����}�X�^�[�^���[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�����ϗ͂��P���ݒ肵�Ă��Ȃ����ɕ\������܂��B�����ϗ͂�V�K�ݒ肵�Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�����ϗ͂��P���ݒ肵�Ă��Ȃ����ɕ\������܂��B�����ϗ͂�V�K�ݒ肵�Ă��������B
�y�������z
�u�����}�X�^�[�^���[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�����ϗ͂��P���ݒ肵�Ă��Ȃ����ɕ\������܂��B�����ϗ͂�V�K�ݒ肵�Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�����ϗ͂̓o�^�p�^�[�����s�����Ă��鎞�ɕ\������܂��B
�S�Ă̏����œo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�S�Ă̏����œo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�y���ڍ����z
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�����ϗ͂̓o�^�p�^�[�����s�����Ă��鎞�ɕ\������܂��B
�S�Ă̏����œo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
�y�������z
�u�����}�X�^�[�^���[�������^�ϗ̓^�u�^�����ҏW�v�ɂ����āA(���ނ�)�����X���b�g�������̏������������ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�����ϗ͂̓o�^�p�^�[�����s�����Ă��鎞�ɕ\������܂��B
�S�Ă̏����œo�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
�y�������z
�u�����}�X�^�[�^���[�������^�ϗ̓^�u�^�����ҏW�v�ɂ����āA(���ނ�)�����X���b�g�������̏������������ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�y���ڍ����z
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�^�����ҏW�v�ɂ����āA(���ނ�)����⑊��ސ��̏������������ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
�y�������z
�u�����}�X�^�[�^���[�������^�ϗ̓^�u�^�����ҏW�v�ɂ����āA(���ނ�)�����X���b�g�������̏������������ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�^�����ҏW�v�ɂ����āA(���ނ�)����⑊��ސ��̏������������ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
�y�������z
�u�����}�X�^�[�^���[�������^�ϗ̓^�u�^�����ҏW�v�ɂ����āA(���ނ�)�����X���b�g�������̏������������ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�^�����ҏW�v�ɂ����āA(���ނ�)����⑊��ސ��̏������������ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�\���v�Z�ݒ�^�ڍ����v�́u�t����f�̌����v�Ƀ`�F�b�N��t�����ꍇ�ɕ\������܂��B
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�t����f�ϗ͂��o�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���ˍޒ[�������^�ϗ̓^�u�v�ɂ����āA�t����f�ϗ͂��o�^����Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�m�F�����P�˃}�X�^�[�ݒ�菇�����Q�l�ɁA�uXstar�œ��͂��������}�X�^�[�v�Ɓu�\���v�Z�p�̋������x�}�X�^�[�v�̖��̂���v���Ă��邩���m�F���������B
��v���Ă��Ȃ��ꍇ�͋������x���A�g����܂���B
�m�F�����Q�ˉΑł������Ɋւ��Ă͉��L�̂R�_�̖��̂������Ă��邱�Ƃ����m�F���������B
�E���}��ɓ��͂��Ă���Αł����̎���
�@���u���퓙���}�X�^�[�^����v�ɓo�^���Ă������̑����Łu�S�A���O���v�Ƀ`�F�b�N�������Ă�����킪�Ώۂł��B
�E�u�����ݒ�^�����ݒ�^�d�l�ؑց^�S�A���O���ΑŁv�œo�^���Ă����������
�E�u�������x�}�X�^�[�^�⋭�����^�Αŋ����v�̋�������
��v���Ă��Ȃ��ꍇ�͋������x���A�g����܂���B
�m�F�����Q�ˉΑł������Ɋւ��Ă͉��L�̂R�_�̖��̂������Ă��邱�Ƃ����m�F���������B
�E���}��ɓ��͂��Ă���Αł����̎���
�@���u���퓙���}�X�^�[�^����v�ɓo�^���Ă������̑����Łu�S�A���O���v�Ƀ`�F�b�N�������Ă�����킪�Ώۂł��B
�E�u�����ݒ�^�����ݒ�^�d�l�ؑց^�S�A���O���ΑŁv�œo�^���Ă����������
�E�u�������x�}�X�^�[�^�⋭�����^�Αŋ����v�̋�������
�Y���ӏ��̒����܂��͒��r�ɋ�����z�u���Ă��������B
�u�����}�X�^�[�^���[�������^�ϗ̓^�u�^�����ҏW�v�ɂ����āA(���ނ�)�����X���b�g�������̏������������ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�����}�X�^�[�^���[�������^�ϗ̓^�u�^�����ҏW�v�ɂ����āA(���ނ�)�����X���b�g�������̏������������ݒ肳��Ă��邩�m�F���Ă��������B
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
 �ڍ���(PDF)
�ڍ���(PDF)
�u�ꉮ-�������ڍ����ɍ�p���������T�v���Z�o���邽�߂̏����̊m�F�����Ă��������B
�i�u�\���v�Z�ݒ�^2�����ށ^���̌����v�Őݒ肵�������j
�����A���������̐ݒ肪�K�Ȃ̂�NG�ɂȂ��Ă��܂��ꍇ�́A�u���̌����^�ڍ����������x�^�ꉮ-���v�̋������x���グ����@�ɂȂ�܂��B
�ؑ����g�H�@�Z��̋��e���͓x�v 2008�N�x��(�O���[�{)�ɂ́u�������r�ڍ����̌������Ɏg�p��������ϗ͂�p���邱�Ƃ��ł���v�Ƃ���܂��̂ŁA�����̏ɉ����đϗ͂�ݒ肵�Ă��������B
�i�u�\���v�Z�ݒ�^2�����ށ^���̌����v�Őݒ肵�������j
�����A���������̐ݒ肪�K�Ȃ̂�NG�ɂȂ��Ă��܂��ꍇ�́A�u���̌����^�ڍ����������x�^�ꉮ-���v�̋������x���グ����@�ɂȂ�܂��B
�ؑ����g�H�@�Z��̋��e���͓x�v 2008�N�x��(�O���[�{)�ɂ́u�������r�ڍ����̌������Ɏg�p��������ϗ͂�p���邱�Ƃ��ł���v�Ƃ���܂��̂ŁA�����̏ɉ����đϗ͂�ݒ肵�Ă��������B
��b�J���̒���ɒ����z�u����Ă���ꍇ�ɕ\�������G���[�ł��B
���ނ̔[�܂肪���������m�F���Ă��������B
���ނ̔[�܂肪���������m�F���Ă��������B
�u�A�������v�͈͓̔��ɂ����b���̑����́u�Z�����́v�̐ݒ肪�����Ă��Ȃ��ꍇ�ɕ\�������G���[�ł��B�u�Z�����́v�̐ݒ肪�S�đ����Ă��邩�m�F���Ă��������B
↑�y�[�W�̐擪�֖߂�